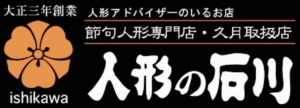京都を代表する京甲冑師
現代の名工 粟田口清信。
伝統を守り続ける職人。
一流の証が随所に。
そんな一流職人とじっくりと時間を使い、特別に仕立てて頂いたのが、この大鎧。

角
角の形を特別に強く逞しく見えるようにと、通常のものより太くし、バランスも悪くならないように、シャープさも出しました。
孔雀の羽のような柄は、一つずつ手打ち、最後に全体が反ってしまうので、職人の感で叩いて調整しています。

本金箔押手彫龍頭
躍動感のある龍。
手彫にて繊細に作られています。
欄間を彫る様に、角や髭、足などは、細部までしっかりと作られています。

金物
彫の深い金物。
プレスで作られる金物とは全然、深み、輝きが違います。
兜で一番有名な牡丹の金物。
一番に咲く花として、縁起がいいものです。

面頬(めんぽう)
きりっとした髭
鬼の形相を表すお顔。
この面頬は鉄板を叩き出して作られています。
深い彫の顔を作るために、何千と叩きます。

組紐
しっかりとした太い京組紐を使用しています。
縁起のいい結びで兜の緒を結んでいます。

糸
兜の後、肩、胴、垂など一定間隔に編まれています。
この糸、一般的な五月人形とは違い、元々の糸が太いものを使用しています。
極上の正絹の糸を使用。伝統工芸品レベルでも最高級のものです。
綺麗に編むために、穴の数は調整して開けます。
通常は穴の数は、鎧の大きさで決まっていますが、粟田口清信の五月人形は、穴の数を随時、調整して作られて行きます。

絞め
兜、肩、垂の最後のバッテンになっている部分は、本革で編まれています。
引き締める色でもあり、悪霊退散の意味もあります。
古来は、燻した革で編まれていたそうです。

垂れ
本金の極上金襴を使用。
この金襴は特別にお願いして使用して 頂きました。
本金の糸は、手をかざすとキラキラと輝きが見られます。
本金の金襴の間。
こんなところにも赤い革が使用されております。

脛当て
手打ちにて叩き出して作られています。
本革で縛り、防御するものですので外れることのないよう、しっかりと結ばれています。
この脛当て。他のものと比べると、厚みがあり、重厚さがよく分かります。
細部までこだわり、粟田口清信のこだわり、人形の石川のこだわり、それがコラボした、最高級の五月人形です。